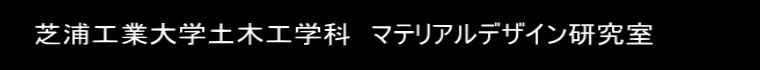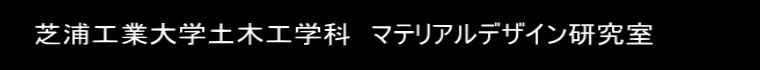�y�{�H�z
���V�^�o�C�u���[�^�[�̎{�H���\���㐫�Ɋւ��錟��
�@�@�@�@�iB4�F���AC�F�G�N�Z���j
�����ޓ��̈ړ�����Ƃ�����U���ƒ��ł߂���Ƃ������U���̃o�C�u���[�^�[�̑g�ݍ��킹�ɂ��A�R���N���[�g�̎{�H���\�Ȃ�тɕ\�ʐ��\�i�\�w�̎d�オ��╨�����ߐ��j�̌����ړI�Ƃ����V�J���o�C�u���[�^�[�̐��\���������Ǝ�����ɂ����Č��؎�������B |



�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������� |