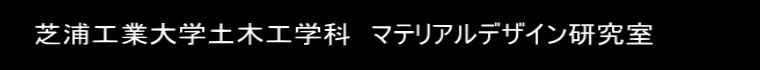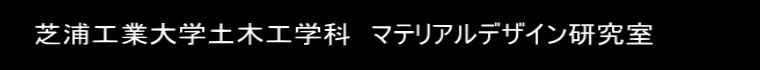�y�{���]���z
���{���̑��Ⴊ�����Z���ɗ^����e���]��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�S���F���c�iB4))
���{�����قȂ�Ό`�������\�����قȂ邪�C�����Z����Z�Ў�������ꍇ�C�Đ��a�̉e�������邽�߂ɁC���̑���m�ɕ\���ł��Ȃ��B�����ŁC��N�x�������������Ԃ̓d�C�j��������p���āC�{���̈قȂ�R���N���[�g�̉����Z����]������B |


�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������ʂ́@������ |