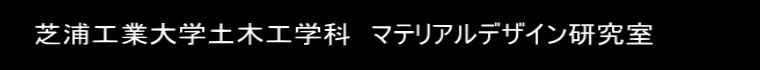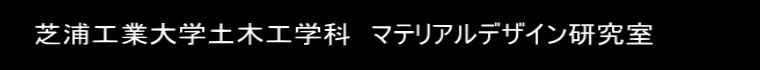�����F�Z�����g�̉����Œ艻���J�j�Y���̌���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�S���F�����iM2))
�����F�Z�����g�R���N���[�g�͕��ʃ|���g�����h�Z�����g��p�����R���N���[�g�Ɣ�r���ĉ����Œ艻�\�͂��傫���Ƃ����B���̂��ߊg�U���ł͂��̐Z����]���ł��Ȃ��ƍl����B�����ŁA���̃��J�j�Y���������̌`�Ԃ̈Ⴂ�ɂ���Đ�������B |
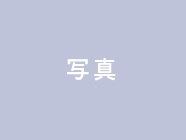 |