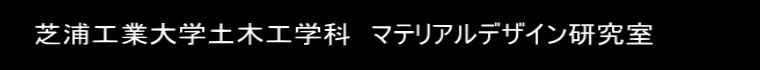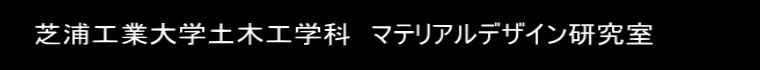|
”土木”と聞くと、3K(きつい、汚い、危険)のイメージが大きいと思います。また、談合や政治献金などの金銭的な話題、無駄な公共投資(「コンクリートから人へ」)の印象が色濃くあると思います。
確かに昔からそのような話題があり、マスコミにも取り上げられてきました。
しかし、本当にそれだけなのでしょうか??
土木は英語では、"civil engineering"と略され、和訳すると”市民工学”です。
古代から、川に丸太を渡して岸から岸へ移動する手段を考えたり、走行しやすいような道路をつくったり、山を迂回しないで通れるようにしたり、移動を便利にするために、鉄道や航空機・船舶が使えるように、線路や空港・港などを整備したり・・・。
このように人々が快適に安全・安心な生活が送れるよう、社会基盤施設(橋やトンネル、道路、鉄道、ダムなどなど)を提供する仕事が”土木”なのです。
当然のことながら、これらの施設は巨大なために、巨額なお金が必要となります。また、このような施設を利用するのは、他でもない”国民”になります。そこで、これらの建設費用は”国民の税金”を利用することになるのです。
税金を使って建設するため、本来ならば国民(市民)の承諾を得る必要があります。しかし、国民全員の意見を集約することは難しいため、国民(市民)の代表者である、政治家(国会議員や都道府県・市町村議員)に委ねるということになるのです。
国土を変えてしまう(地図に残る)建造物を建設することになるわけですから、その計画は壮大なものになります。また、不要なものをたくさん作っても仕方がありませんので、本当に必要なものをできるだけコストを抑えて建設していく必要があります。
そのためには、構想・計画・設計を緻密な議論の上に作り、建設に至ります。
周囲で行われている建設は、そういった長い年月の議論や計画を経た上で、実行されているものです。
建設現場は、確かに外の仕事でもあり、時には危険や大変な状態もありますが、世界に一つだけ(他に同じものはない)の巨大な構造物を、社会のため、国民のために建設しています。
建築家のようにスーパーヒーローや有名なデザイナーが目立つようなことはあまりありません。しかしこれは、一人の力では到底できないような、大型構造物の建設を考えると自然のことかもしれません。
土木工学は、このように設計には理系科目である物理や数学が必要になりますが、環境や材料を考えると化学や生物の知識も必要ですし、社会を考慮すると、経済や政治、歴史や地理、気象条件(地学)なども重要です。また、体力や情報の能力も必要です。さらに、国民や市民との合意形成や説明をするためには、国語や海外では英語も必要となります。このように幅広い知識を習得して、日本、世界を変えていく技術者を目指してみてはいかがですか?
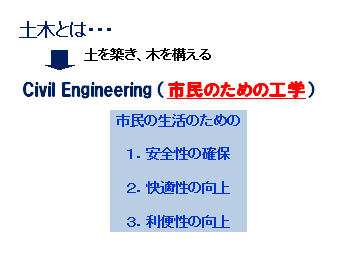
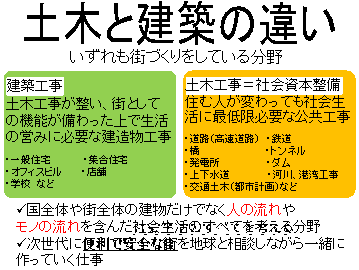
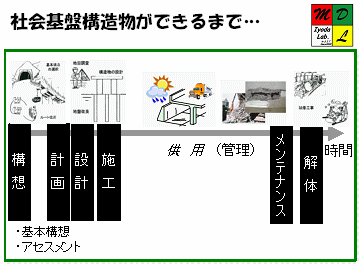
|